スーパーマーケットの冷蔵棚の“赤パケ”でおなじみ、おかめ納豆「極小粒」。白ごはんにすっとなじむ王道の味で、毎日でも食べ飽きない定番です。本記事では、そんな「極小粒」の魅力を紹介していきます。
それでは早速納豆レビュー!
タカノフーズ「極小粒」のお味

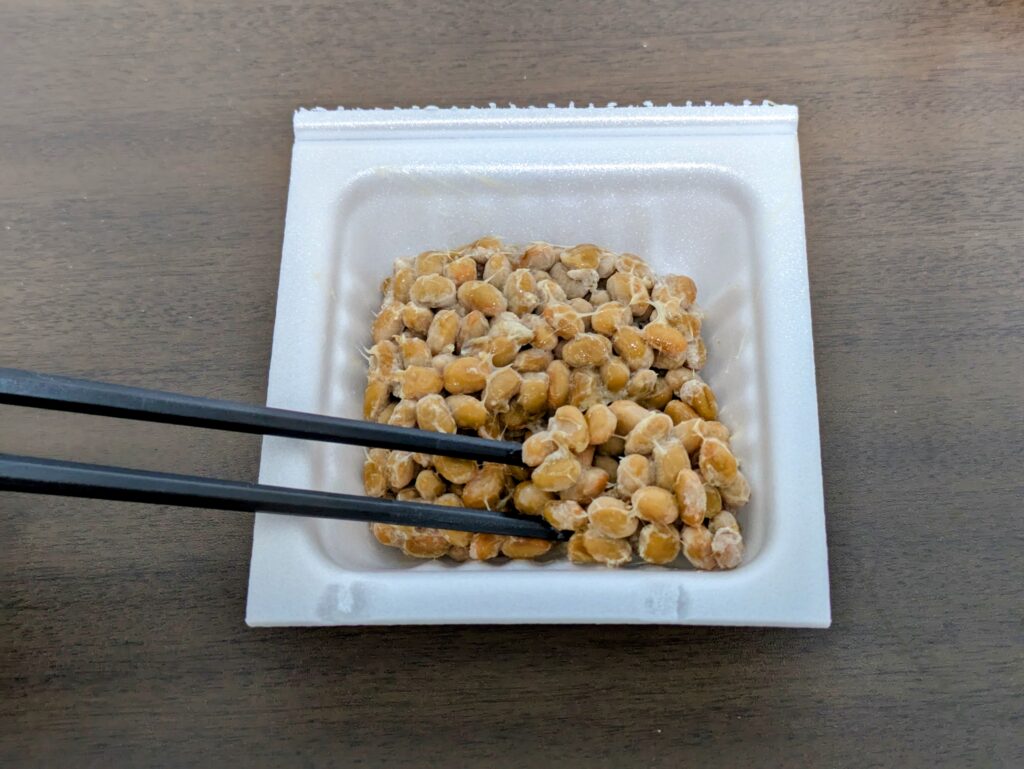
うん!美味しい。安心しますね。あ〜これこれ、これだよ、ずっと食べてきたのはこれです。お手頃価格なのに、安定のこの美味しさ、納豆といえば、タカノフーズ「極小粒」ですね。
- 粒サイズ:2 / 5
- ふわふわ:3 / 5
- 甘さ:2 / 5
- 総合:2 / 5
小粒納豆の食感を楽しめます。極小粒ながら、しっかりふわふわ食感を残しています。この技術を、これだけ大量生産できているのはさすがはタカノフーズさんですね。
しかし、後味に、大豆独特のえぐみが、わずかに口に残る気がします。そこは少し残念なポイントではありますね。
1982年、「極小粒」が朝ごはんを変えた
タカノフーズの社史の中でも、1982年はターニングポイント。この年に登場した「極小粒」が大ヒットして、同社のポジションを一気に押し上げました。
なぜ「極小粒」はここまで刺さったの?
答えはシンプルで本質的。“食べる人(顧客)中心”の設計だったからです。
もともと納豆の本場・水戸では、豆腐や味噌に向かない小粒大豆を上手に活用して納豆文化が育ってきました。タカノフーズはその延長線上で、ただの“小粒”ではなく、さらに一歩攻めた「極小粒」という価値を打ち出したんです。
体験がちゃんと良くなる
実際の感想でも「ご飯によく絡む」「食べやすい」という声が多いですよね。
粒が小さいから、混ぜたときにご飯との一体感がぐっと上がる。納豆のいちばん一般的な食べ方=ご飯にのせて食べる体験を、物理的にアップデートしたわけです。
作り手目線から、食卓(顧客)目線へ
ここが最大のポイント。
「納豆を作る」という作り手の発想から、「ご飯と一緒に、もっとおいしく食べられる納豆を作る」という食卓(顧客)起点の発想へ。
この視点の切り替えが、そのまま商品コンセプトの核になりました。単なるパッケージやネーミングの妙ではなく、食感・混ざりやすさ・食べやすさといったリアルな体験価値を磨き込んだから、1982年の“極小粒”は市場で勝てたんんですね。
おすすめの食べ方・簡単アレンジ
王道の王道で、素晴らしいぐらいに、どれにもよくあいます。まさに冷蔵庫に常備しておきたい「万能選手」!
- 定番:ねぎ+卵黄/卵かけご飯にオン
- 5分丼:キムチ+胡麻+小ねぎ
- さっぱり:大葉・みょうが・ポン酢少々
- パン派:納豆トースト(チーズ少量+のり)
私の個人的な推しは、このちょうど良い粒サイズの「極小粒」は卵と合わせるか、もしくはそばと絡めて冷やし納豆せいろにするのが夏の定番です。
原料と“安心”の裏側
原料大豆:アメリカまたはカナダ産の丸大豆を使用しています。遺伝子組み換え大豆の混入を防ぐために、分別生産流通管理を行っているそうです。原材料欄に明記されています。タカノフーズ株式会社
納豆菌の研究力:納豆菌は“自社オリジナル”を2200種以上ストック。商品ごとに狙いの香り・粘り・食感へ調整しています。 タカノフーズ株式会社
追記:新商品?
タカノフーズさんのHPを確認していたところ、「秋冬限定商品 明太子納豆」を見つけました!食べてみたい!〇〇のスーパーで見かけたよ〜と言った情報がありましたらぜひ教えてください。


コメント