今回は、千葉県のある町を訪れた際に立ち寄った八百屋さんからお伺いした、「八百屋の現状、問題」に関して共有させてください。端的に申し上げると、地方の八百屋さんの経営は非常に厳しい状況とのことでした。
仕入れ問題
近くの市場に買い付けに行っても、すでにスーパーなどが大量に仕入れを契約しているために、そもそも買い付けられる商品が少なくなっている。
売り先の問題
地域の八百屋のお客さんは、個人、保健所、介護施設など。小学校、保育園などは入札競争が激しく、なかなかできない。
お客さん離れ、新規顧客獲得の難しさ
地方の人口は目減りしていく中で、当然ながらお客さんが少なくなっています。また、八百屋さんといえば、生鮮品に限った販売。野菜、青果物のみならず、肉、魚などの揃うスーパーには、優位性で劣ってしまい、お客さんはどんどんスーパーに流れてしまいます。
加工品販売取り締まり強化
こんな状況でも新たな取り組みとして、仕入れた野菜を用いて漬物などの販売をしたいという思いもあったそうですが、保健所による加工品販売の取りしまりが強まり、地方の八百屋さんが販売にこぎつけるにはハードルが上がってしまいました。
保健所による加工品の販売取り締まり、法改正と多様な販売形態で監視の目は厳しく
近年、食品衛生法の改正やインターネット販売の普及などを背景に、保健所による加工品の販売に対する監視の目は実質的に厳しくなっているんだ。
食品衛生法改正による営業許可制度の厳格化
2021年6月1日に完全施行された改正食品衛生法により、営業許可・届出制度が大きく見直されたようだよ。これにより、許可が不要であったり、届け出の対象外であったりした事業者も、新たな規制の対象となるケースが出てきたんだ。
つまり独自に加工品を販売しようとすると、管轄地域の保健所への申請と、条件を満たすための設備が必要となります。例えば、弁当や惣菜を製造する場合は「そうざい製造業」、ジャムやジュースの場合は「菓子製造業」や「清涼飲料水製造業」、漬物の場合は「漬物製造業」といった許可を、管轄の保健所から取得する必要があります1。これらの許可申請には、それぞれ手数料が発生し、一例として、そうざい製造業の申請手数料は21,000円、菓子製造業は14,000円、漬物製造業は14,000円です。また、許可を取得するためには、保健所が定める施設基準(例:シンクの数、手洗い設備の設置、十分な換気など)を満たす厨房設備を整える必要となります。このように、漬物を販売したいと思っても地方の八百屋さんにとって、多額の初期投資がハードルを高くしてしまいました。
新世代の八百屋さん
そんな厳しい現状の中でも新たなビジネスモデルとして注目を集める八百屋さんがあります、それが東京を中心に展開する「旬八青果店(アグリゲート)」と関西を中心に展開する「八百鮮」です。
旬八青果店(アグリゲート)
伝統的な八百屋のビジネスモデルを根本から覆した代表格とも言われており、その成功の核心は、アパレル業界の「ユニクロ」にもなぞらえられるSPA(製造小売)モデルと、徹底したデータ活用にあります。
- SPA(製造小売)モデルの導入: 旬八青果店は、卸売市場を介さず、全国の生産者から直接商品を仕入れる、あるいは連携することで、生産から流通、小売までを一気通貫で管理しています。これにより、中間マージンを徹底的に排除し、高品質な青果物を「適正価格」で消費者に提供することを可能となりました。さらに生産者と直接繋がることで、消費者のニーズを迅速にフィードバックし、商品の質を継続的に向上させる情報循環サイクルを構築している点も強みであります。
- DX(デジタルトランスフォーメーション)の徹底活用: 従来の八百屋さんが店主の勘と経験に頼ってきたのに対し、旬八青果店はデータに基づいた定量的な経営を実践している。自社で開発した仕入れ管理システムとPOSレジを連動させ、個々の品目単位で粗利率を厳密に把握・可視化しています。これにより、単に粗利率が高いだけでなく、販売量も見込める商品を戦略的に仕入れることが可能となります。
八百鮮
「八百鮮」は、旬八青果店とは対照的なアプローチで急成長を遂げているベンチャー八百屋さんです。
- 徹底した「個店主義」: 大手スーパーが一括で商品を仕入れるセントラルバイイング方式を採るのに対し、八百鮮では各店舗のスタッフが毎朝市場へ出向き、その日の状況に応じて自分たちの裁量で商品を仕入れ、価格を決定します。これにより、画一的な品揃えを避け、常に最も新鮮で最もお買い得な商品を顧客に提供することが可能となりました。
- 在庫ゼロ経営: 八百鮮のビジネスモデルは、「その日に仕入れたものは、その日のうちに売り切る」。在庫を持たないことで、商品の鮮度を究極まで高めると同時に、保管コストや廃棄ロスを限りなくゼロに近づけているそうです。売れ残った商品は夕方に値引きするなどして売り切るため、翌日にはまた全く新しい商品が店頭に並びます。
追記
新しい風が吹きつつある八百屋さんビジネス。今後の変化が楽しみですね。今回紹介した「旬八青果店」「八百鮮」、近くにあるよ!という方がいましたらぜひ足を運んでみてください。
それにしても、どちらも都心出店、、、地方の八百屋さん、地方のお菓子屋さん、地方の農家さんの収益性が向上して地域全体が活性化する活路を見出せたらと思います。
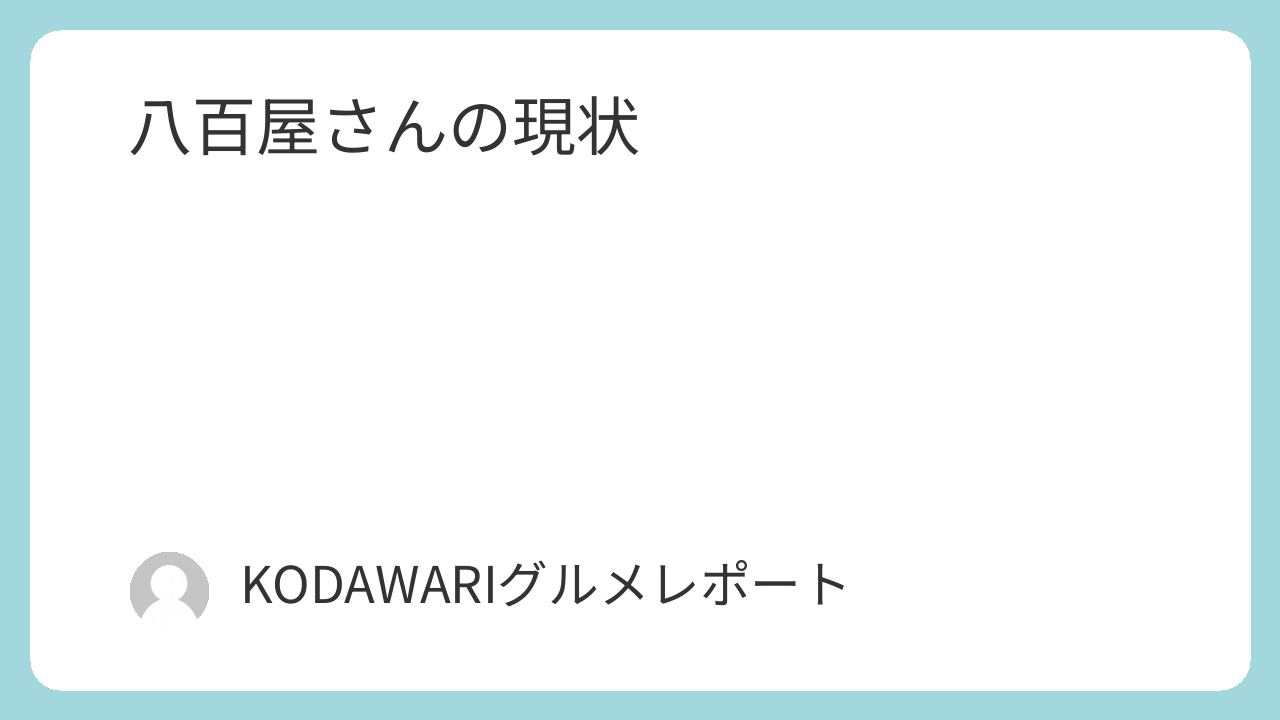


コメント